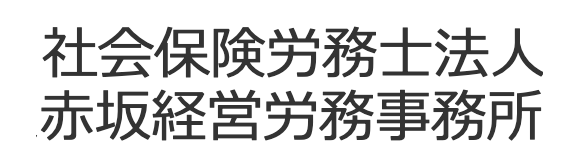経済は、十数年続いたデフレから、インフレ経済へと大きく舵が切られようとしています。すでに消費税が上がり、財布を直撃する一方で、介護や建設など業界によっては人手不足が目立つようになり、さまざまな形で「賃上げ圧力」が急速に高まっています。
人件費は三大経費の1つです。適正な人件費管理なくして、健全な経営は成り立ちません。
生計費や同業他社の賃金水準との比較分析を行った結果、自社の賃金水準が相当低いことが判明した場合、個別賃金水準の引き上げが必要です。これは、人事制度だけの問題ではなく、経営的な問題と大きく関係します。
最近「賃金制度・給与体系」を変更されたでしょうか。
賃金制度・給与体系を再構築する必要性は、次の事実からも出てきています。
少子化により、 労働人口が減少していくことが明確となり、中小企業は、今後「採用」に苦労するようになります。
そこで、「従業員が働き甲斐のある会社」になろうと考えている会社が多くなっています。
「従業員が働き甲斐のある会社」になるためには「賃金の問題」を避けることができないのです。

求人難の時代に入った事については、多くの中小企業で実感しつつあります。
そこで、必然的に「賃金制度・給与体系再構築」を行う企業が増えるのです。
中小企業にこそ、その必要性があるのです。
つまり中小企業は、「求人対策」のためにも、「賃金制度・給与体系」を見直さざるを得なくなっているのです。
「賃金制度・給与体系」を見直す際には、現在の賃金がどのような状態になっているのかを多角的に分析しておく必要があります。いわゆる「賃金分析・診断」ということです。
なぜなら、例えば、能力主義や成果主義の賃金で自社では能力ある者は高い配分になっているという場合でも、同業他社との比較ではそれほどでもない、という場合もあるからです。
あるいは、賃金の配分が不適切になっている場合も多いからです。
賃金診断のポイントとして次のことがあげられます。
①生産性と賃金のバランスはどうか
②賃金にゆがみ・散らばりはないか
③自社の賃金は他社と比較して高いのか、低いのか
④標準生計費から見た場合に自社の個別賃金の妥当性はどうか
⑤めざすべき体系と水準は
賃金制度の見直しについては、企業の目標を達成するために自社では何を社員に求めるのか賃金・人事制度の見直しは、それを問い直すことから始まります。
これからは、業種、会社ごとの特質によって賃金体系を構築していく時代になったと言えます。もっと言えば、会社の業態にあった賃金体系を採用しないと厳しい時代を生き残れないでしょう。
自社に適した賃金体系はどれでしょうか?
年功給
<デメリット> 役割・責任が不明確 → 個人評価ができない
<メリット> 安定感が抜群で、平均的社員の定着率が高い
職能給
<メリット> 会社にとっては、納得性の高い昇格・評価基準になり得る
<デメリット> 年功的な運用がもたらす「賃金と能力のミスマッチ」
成果主義賃金
<メリット> 業務変革へのチャレンジを引き出すことができる
<デメリット> 目先の業績のみを追いかける
それぞれにメリット、デメリットがありますが、賃金の基本的な考え方は、役割基準です。
企業の強さは人材力です。社員の「ヤル気」を引き出す仕組みをつくらなくてはなりません。その「仕組み」を実現させるのが役割・貢献を基軸とした人事システムです。
この人事システムは企業の実態を踏まえた実力主義の人事・賃金制度です。
賃金人事のテーマを一連の作業として合理的に解決できれば、難しいと考えられてきた賃金人事の要点をクリアーすることができるのです。
今、必要な賃金制度・給与体系の見直しのポイントは
 人事・労務
人事・労務