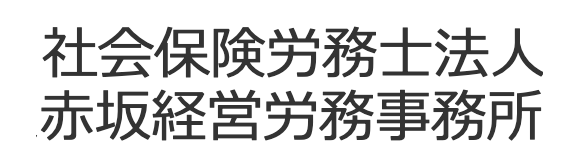コーポレートガバナンス(企業統治)の考え方が注目されてからかなりの時間が経ちました。しかし、どのような形での統治が望ましいのか、明確な答えはまだ出ていません。
「コーポレートガバナンス(企業統治)」の概念が日本で広がりを見せたのは、1990年代のことです。バブル崩壊の煽りをうけて、多くの企業が不正配当、不正経理、粉飾決算などを行なっていたことが発覚したからです。
また、2000年代に入って頻発した食品偽装問題もコーポレートガバナンスに関する議論ともちろん無関係ではありません。不祥事の発生を防ぐには、誰がどのように企業を統治したらいいのかという観点がクローズアップされました。
A社は半導体を製造・販売するメーカーで、創業90年と社歴は古く、前身は印刷業を営んでいたそうです。会社が飛躍したのは半導体関連の事業を手がけ始めた1970年代のことです。
歴史があるだけに、これまでにさまざまな浮き沈みがありました。最も近いところでは、経営幹部による横領事件です。外注先の担当者と共謀し、水増し請求を繰り返し、差額をふたりで懐に入れていたのです。
このときからA社はコーポレートガバナンス(企業統治)を強く意識するようになったのです。
自社で起こった事件、また企業不祥事の頻発という社会情勢を受けて、A社でも対策を講じる動きが急がれました。何かしなければまずいんじゃないかという雰囲気が、社内に漂っていたといいます。
それでA社で実施されたのが、社外取締役の配置でした。メインバンクの助言を受けて、社内の監視の目を強化することを目的に配置されたのです。
横領事件から社外取締役の設置まで、この一連の動きは、A社三代目のころの出来事でした。
それから十数年を経て、社外取締役の存在がA社で当たり前になった今、先代の長男がA社四代目の経営者となりました。
海外のビジネススクールで学んだという経歴の持ち主です。
帰国後にA社に事業部長として入社し、多くのプロジェクトを成功させたのち、周囲から望まれて社長に就任したという経緯があります。
ところが、A社長自身には違和感があったといいます。その違和感の正体が就任自体にあるのか、それとも他にあるのか、最初は分からなかったそうです。
しかし、社長としての日々を過ごすうち、やがて違和感の正体がはっきりしてきました。それは、「監視の目」でした。かつての横領事件、そしてそれ以来、社外取締役が配置されたことはA社長も承知しています。営業部長時代にも、不正をより厳格に防止するための施策が経営陣によって実施されました。
先代の時代に打ち出された決め事が、自分が経営者になってみると、より強く自分を縛りつけているという感覚をA社長はもったといいます。
もちろん、それらはかっての経験に学び、不正を未然に防ぐために必要であることをA社長は否定しませんでした。社外取締役による監視も含めてです。
しかしながら、監視をきつくするだけが不正を防止する手段であるかというと、A社長にはそうは思えなかったのです。
A社長が今にして覚える違和感の端緒は、留学時代にあったのかもしれません。
ビジネススクールの授業では、コーポレートガバナンスについても学びました。

そこで教えられたのは、「経営者性悪説」というべきものでした。つまり、経営者というのは、自己の利益の追求にだけ関心があり、利益の中身は富だったり、名声だったり、あるいは権力だったりとさまざまですが、いずれにしても経営者の行動原理は自己の利益にあるというものでした。
だからこそ、自己の利益のために、してはいけないことをさせないように決め事をつくらないといけないという考え方です。
経営者は自己の利益にばかり関心があるという捉え方から生まれたのが、監視の強化であったり、業績に応じて巨額の報酬を与えるというやり方です。つまり、あからさまなアメとムチです。
たしかに、そのような経営者が存在することは否定できません。ですから、経営者の倫理を最低限のラインで保持するには効果的かもしれません。
また、どんなに立派な経営者だとしても、富、名声、権力を求める気持ちがまったくゼロということはないと、A社長も十分に理解しています。
しかし、そんな経営者像を基準にしてしまったら、手から漏れ落ちるものが大きすぎる気がしてならなかったのです。
A社長は事業部長時代、数々のプロジェクトに他の社員とともに取り組み、成功を収めてきました。それは決して監視システムが働いていたから生まれた成果ではないと信じています。
そして社長に就任した今、自分たちのもてる技術で他人のためになるものを生み出したい、社員とその家族の生活を守りたい、関係する人々と信頼関係を築きたい、といった気持ちが強くなっていることに改めて気づいたといいます。A社長はこれらを自社のコーポレートガバナンスの根幹に据えたいと考えたのです。
それでも、A社長は従来のコーポレートガバナンスを全否定するつもりではないそうです。ただし、それはあくまで補完的な位置付けであって、主従の従であると捉えています。
主はあくまで責任感や使命感、利他心や相互信頼です。社内の具体的な取組みとして、経験の浅い社員にも仕事を任せることにしました。社員を信じていることを伝え、社員には責任感をもってもらうためです。
コーポレートガバナンスの対象は、経営者および経営陣でした。彼らに対してアメとムチで対処するのがその本質ならば、やがてその風潮は会社全体に浸透していくことでしょう。
会社にとって経営者の影響力は強く、経営者が監視システムを受け入れるならば、その態度は社員にまで波及していくはずです。
ですから、コーポレートガバナンスは経営者だけでなく社員の問題でもあり、どんな会社にしたいか、どんな経営をしたいか、社員にどんな働き方をしてほしいかまで広がっていきます。
「企業文化の浸透」という視点で、コーポレートガバナンスについて再考してみてはいかがでしょうか。