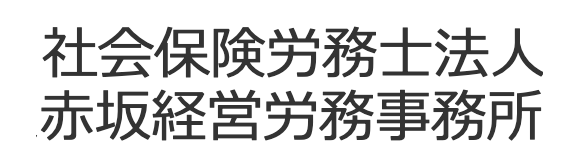2020年6月1日から「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が施行(中小企業は2022年4月1日)され、企業には職場におけるパワハラを防止する措置が義務づけられました。
コロナの影響を受けて、テレワークなど新たな働き方が進められる中、本年、措置が義務づけられたパワーハラスメントについて考えてみたい。
パワハラは法律で具体的に明記されていないものの、厚生労働省で以下のように定義されています。
「(1)優越的な関係を背景とした言動で(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより(3)労働者の就業環境が害されるもの」
また厚生労働省は、パワハラの代表的な行為を6つの類型に分けています。これらの行為がパワハラかどうかを判断する基準になるので確認していきましょう。
典型的なパワーハラスメント行為として、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害の6つの行為類型があります。
ただし、これらは職場のパワーハラスメントすべてを網羅するものではなく、これ以外は問題ないということではないことに留意が必要です。
(1)身体的な攻撃
殴る・蹴る・物を投げつけるなど、いわゆる暴力を振るうことです。
・該当する例
上司が部下に対して、殴打、足蹴りをする。
・該当しない例
業務上関係のない単に同じ企業の同僚間の喧嘩。
(2)精神的な攻撃
言葉の暴力によって、精神的な苦痛を与えるものです。相手を侮辱し、人格を否定するような行為全般が該当します。
・該当する例
上司が部下に対して、人格を否定するような発言をする。
・該当しない例
遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ、再三注意 してもそれが改善されない部下に対して上司が強く注意をする。
(3)人間関係の切り離し
挨拶や仕事のやりとりで無視をするような環境をつくり出してしまうことがあてはまります。
・該当する例
自身の意に沿わない社員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする。
・該当しない例
新入社員を育成するために短期間集中的に個室で研修等の教育を実施する。
(4)過大な要求
あきらかにできそうにない仕事を強制することはパワハラにあたります。
・該当する例
上司が部下に対して、長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる。
・該当しない例
社員を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せる。
(5)過小な要求
あきらかに本人の能力より下回る仕事だけしか与えない、あるいは仕事をまったく与えないこともパワハラに該当します。
・該当する例
上司が管理職である部下を退職させるため、誰でも遂行可能な受付業務を行わせる。
・該当しない例
経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせる。
(6)個の侵害
いわゆるプライバシーの侵害です。
・該当する例
思想・信条を理由とし、集団で同僚1人に対して、職場内外で継続的に監視したり、他の従業員に接触しないよう働きかけたり、私物の写真撮影をしたりする。
・該当しない例
社員への配慮を目的として、社員の家族の状況等についてヒアリングを行う。

ハラスメントがなぜ起こるのかその発生の原因を知ること、またハラスメントが起きる背景を知ることは、起きているハラスメントを理解するうえで大変役に立ちますし、新たなハラスメントを予防していくためにも重要なものになります。
ハラスメント予防対策においても企業の責務として、「パワーハラスメントが発生する原因や背景を労働者に周知、啓発すること」が求められています。
「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」問題が社会問題として顕在化した背景には、企業間競争の激化による従業員への圧力の高まり、職場内のコミュニケーションの希薄化や問題解決機能の低下、上司のマネジメントスキルの低下、上司の価値観と部下の価値観の相違の拡大など、多様な要因があるとされています。
(1)働く環境の変化
近年はさまざまな人が、異なった雇用形態でひとつの職場に集って働くことが当たり前になってきてました。
2人以上の人間が集えば意見の衝突は起きます。それがさまざまな立場で、異なった考えや経験をもった世代も違う人同士であれば、なおさら価値観の相違による衝突が起きるのは避けられないでしょう。
(2)経営環境の変化
近年の職場環境の特徴について以下のようにいわれます。
・一人あたりの仕事量が増えた
・求められるスピードが速くなった
・ミスに厳しくなった
このような「亡しくて余裕がなく、緊迫した職場環境」では自然にストレスが高まり、いらだつ職場環境となりがちです。
(3)働く人の意識の変化
終身雇用、年功序列が崩壊したことによって転職に対する抵抗感が弱まりました。それにより以前ならば「こんなことを言ったら会社に居づらくなる」といった考えから躊躇していた会社への批判や苦情が言いやすい状況になってきました。
さらに家庭や教育の場で強い指導をすることが減っています。そのため社会に出てはじめて「強く叱られる」「理不尽な要求をつきつけられる」経験をする若者が戸惑い、つぶれてしまうといった現象も目立ってきています。
(4)パワーハラスメントの認知度の向上
仕事をしていくうえでハラスメントに類するような言動を一度も見聞きしたり体験したことがない人は少ないと思います。大なり小なり「なにかおかしい」[やりすぎ]と感じながらも、仕方のないこと、我慢しなくてはいけない個人的なこととしてやり過ごすことが多かったと思います。最近では「パワーハラスメント」という言葉の認知度は高まり、いまや日常用語レベルまで普及していると思います。
社会認知度の向上は、労働相談の増加につながります。
いま労働相談で一番多いのが、この職場内でのいじめ・嫌がらせ間題です。

次に職場のなかでハラスメントが起きた場合、どのようなところにどのような影響が起きるか考えてみましょう。
(1)被害者への影響
繰り返し非難されたり否定されたり、身体的攻撃を受けたりしながら行う仕事は、かなりのストレスを伴います。出社することを考えるだけで憂鬱な気持ちになり職場に向かう足は重くなってしまうでしょう。不安や恐怖を感じながらでは仕事のパフォーマンスは著しく低下し、十分な能力の発揮は難しくなります。
パワハラは被害者にさまざまな影響をもたらし、人生を大きく変えてしまう影響力を持っています。
(2)加害者への影響
パワハラ行為者であると認定され、懲戒処分に相当すると判断されれば、就業規則等に基づいて、けん責・減給・出勤停止・論旨解雇・懲戒解雇などの処分を受けることになります。懲戒処分にならない場合でも、被害者への謝罪や関係改善、不利益回復、職場環境の回復などに努めなければなりません。
さらに損害賠償責任を負うこともありますし、刑事上の責任として暴行罪や傷害罪などに間われ、刑事罰を受ける可能性もあります。
またパワハラを行ったことで、「ひどいことをする人」「パワハラ体質の人」という目でみられ、加害者の個人的信用が失墜し、人間関係も壊れる危険性があります。
(3)周囲への影響
パワハラに関する相談があった職場の共通する特徴として以下のものがあります。
・残業が多い/休みがとりにくい
・上司と部下のコミュニケーションが少ない
・失敗が許されない/失敗への許容度が低い
このような職場では「助け合わない風土」「ギスギスした人間関係」「上下関係が絶対的な関係性」ができやすく、それによりハラスメントの被害者だけでなく、他の従業員全体の意欲の低下や能力発揮の低下を引き起こすことにつながっていきます。
(4)会社への影響
・モラールの低下
・人材の流失、採用難
・訴訟による賠償
・企業イメージの悪化
・事案対応のための費用・時間の負担
職場環境の悪化はその職場で働く人のモチベーションの低下につながり、それにより職場のモラールの低下が起きます。組織の活力低下やモチベーションの低下は作業効率の悪化やミスの増加を招き、結果職場の生産性を低下させます。
また、ハラスメントに対して何も対策を講じずにその状態を許してしまっている職場では退職者が増加し労働者の定着率の低下をもたらしますし、新しい労働者も入ってこなくなります。
それだけでなく「企業のイメージの悪化」につながる大きな間題になります。
職場のパワーハラスメントは、いったん事案が発生してしまうと、その解決に時間と労力を要します。
まずは問題が大きくならないような対応をとることが重要です。
窓口に相談が持ち込まれた場合の対応を見ていきます。
相談者のヒアリングは、パワハラ問題の解決に向けた一番重要なプロセスです。
(1)導入は雰囲気づくりから
相談を受けるときには、安心して話してもらえる雰囲気をつくることから始めます。
(2)じっくりと話を聴く
ヒアリングの目的は事実関係を確認することですが、あまりにも事務的に対応すると、問題がこじれることがあります。初期段階においては、「感情への配慮」が何よりも大切です。
(3)時系列で内容を確認していく
ある程度、相談者が話し終わったら、話を整理するために、ポイントを絞って確認していきます。
時系列に沿って確認していくと、内容を整理しやすいかもしれません。
ここで見逃されがちなのは「どんなふうに」です。パワハラの場合は、言動の「態様」が判断ポイントになりますので、どんなふうに言動が行われたかを確認します。
(4)コミュニケーション状態も確認
相談者と行為者の普段のコミュニケーションがどのような状態であったかを確認して
おくことも重要です。コミュニケーションは、状況を改善するためのカギとなるものです。
コミュニケーションについて聴いておくと、当事者間の関係調整のときにも役に立ちます。
職場におけるパワハラに注目が高まるなか、気になるのはパワハラを職場内で問題視しすぎると上司が萎縮してしまい、積極的な指導に慎重なりすぎることです。
パワハラ研修の副作用として「モノ言わぬ上司問題」が発生することがあります。パワハラについて学んだあと、パワハラを必要以上に意識しすぎるあまりに上司が行うべき指導やマネジメントができなくなってしまうことです。
もし「部下が会社に対してパワハラ申告をした」場合、その成否を会社が公正な調査を行ったうえで判断してくれないということになれば、上司は萎縮し部下への指導を躊躇するようになります。
そうならないためには会社で前もって適正なハラスメント解決のためのシステムをつくっておくことが必要になりますし、上司としては自分の言動が業務を円滑に遂行するために必要な「適正な業務命令」なのか、もしくはそこから逸脱した「パワハラ」であるのかを区別する必要があります。
部下を持つ立場であるならばパワハラと言われない叱り方を身につけておくことが必要不可欠です。