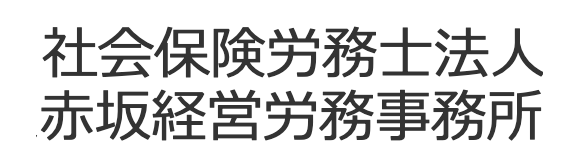ビジョンの大切さを否定する経営者はおそらくいないでしょう。そして、ビジョンの共有がもたらす効用も。しかしながら、実際にビジョンが完全に共有されている会社の比率は驚くほど低いのです。
役員クラスでもビジョンの共有が十分にできていないことがあります。これではビジョンを実現するどころか、その下部に位置するミッションの遂行において混乱をきたしても不思議ではありません。
ビジョンの大切さを認識していながら、なぜこんなにも共有ができていないのでしょうか。
A社長とBさんの出会いは、共通の知人にお互いを紹介されたとある会合に遡ります。
会話の中で、「企業の方々はビジョンの共有が大事とおっしゃいますがいますが、ビジョンが経営幹部に共有されている例を私は見たことがありません。
「経営幹部がビジョンを理解していない?」
 そんなことがあり得るのかと率直に思ったのです。
そんなことがあり得るのかと率直に思ったのです。
「試しに明日、幹部を集めて「我が社のビジョンは何か」という単純な質問を投げかけてみてはどうです。おそらくA社長の予想とは違った結果が出ますよ」との言葉を残し、その日の会話は終えたそうです。
明くる日、A社長はBさんの言葉通りのことをしてみたそうです。
その結果はA社長を愕然とさせるものでした。
まったく思いもよらなかったことを書いてくる幹部が何人もいたのです。
その時、Bさんの言った言葉が蘇りました。Bさんはこうも言っていたのです。「経営幹部でもそうですから、一般社員はなおさらです」と。
A社は工作機械を製造するメーカーです。
社員には常日頃、「なぜ我が社はこの工作機械を製造するのか」をA社長は語ってきたつもりです。
それは「お客様の立場に立って、世の中を豊かにする企業になる」というものです。これがA社の「ビジョン」でした。そして、ここから派生する個々人がやるべき仕事が、A社では「ミッション」と位置づけられていたのです。
ただし、それらはBさんに言わせれば、曖昧模糊なものでした。Bさんの定義では、ビジョンとは「組織のメンバーが力を合わせて実現を目指す夢のあるゴール」のことです。
また、ミッションとは、「ビジョンを実現するために必要な短期的な目標」のことです。
この定義に対して、元よりA社長に異論はありませんでした。しかし、A社長とBさんとの間には、その「実践」においてギャップがあったのです。それらは「簡潔明瞭」でなければならないというのがBさんの主張です。
A社のビジョンやミッションは確かに「簡潔」ではあります。しかし、「明瞭」ではありません。
「お客様の立場に立って、世の中を豊かにする企業になる」とは、どんな風に世の中を豊かにするのでしょう。
また、ミッションにしても同じです。例えばA社では過去に、「売上を20%上げる」と「利益を3%向上させる」というミッションが混在していたことがあったそうです。
これでは売上を優先すべきか、利益を優先すべきか分かりません。現場は混乱します。
優先すべきミッションを上司が正確に把握していないのですから、部下だって同じです。となれば、部下に権限委譲などできるはずがありません。
つまり、ビジョンやミッションが明瞭でないため、方針がはっきりしない。そのため部下は躊躇し、その様子を見た上司は部下を1から10までコントロール、雁字搦めのの組織になっているという傾向があるのです。
Bさんによると、軍隊ではミッション遂行の場面で、兵士の行動は兵士の裁量に任されるそうです。
戦場の状況は刻々と変わるわけで、兵士の行動一つひとつを命令で縛っていては、現実問題としてミッションは遂行できないのです。
ただし、これには前提があります。ビジョンとミッションが簡潔明瞭に提示されていて、それをすべての人間が理解・共有している場合に限ります。つまり、「何のためにやるか」「何をやるか」を全員が十分に理解している状態です。
そうして初めて「どうやってやるか」の部分の権限を現場に委譲できるのです。
また「どうやってやるか」を部下に任せると責任感が生まれ、実際にミッションの遂行率は格段に上昇するそうです。
しかし、軍隊において「どうやってやるか」が現場の兵士の判断に任される最大の理由は、Bさんによると「そうしないと、兵士が死んでしまうから」だそうです。
予測不能な状況に対してあらかじめ細かい指示を出してコントロールするほど、兵士の死ぬ確率が高くなるのだそうです。
戦場においては、兵士の生還が最優先されます。これが不思議なことに、兵士が生きて戻ることを最優先して権限委譲すると、生還率のみならずミッションの遂行率も高まるのだそうです。潜在能力が極限まで引き出されるからでしょう。
この考え方に触れたA社長は、ビジョンに具体的な夢のあるゴールを描き、そのためになすべきステップを簡潔明瞭に設定し直したそうです。
以後、A社のミッション達成率は確実に上がり、日々ビジョンの達成に近づいていることを実感しているそうです。
実際のところ、ビジネスの世界において、一つのミッションの成否が即時に社員の生死に関わることはほとんどありません。
しかしながら、結局のところビジネスも生きるか死ぬかであり、ミッションの成否が全社員の生活につながっており、生きるか死ぬかに違いはありません。
であれば、軍隊が兵士の生存率を上げると同時にミッションの成功率を上げる方法を学んでもいいのではないでしょうか。
軍隊とは硬直した組織とのイメージがあるかもしれませんが、生き残るためには柔軟にならざるを得ないようです。
もしかしたら、生死がリアルでないだけ会社組織のほうが硬直している可能性があります。ビジョンとミッションを「簡潔明瞭」という観点で見直してみてはいかがでしょうか。