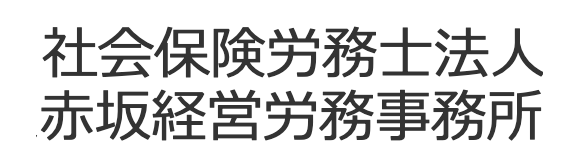コロナ対策に成功した国々、共通点は女性リーダーの存在など、リーダーシップが問われています。
新型コロナウイルスの感染について、自治体の会見がリアルタイムに報道されることから、多くの人が自治体の発表する情報に注目をしています。
情報公開に対する自治体の姿勢や、ひいては自治体のトップである首長のリーダーシップが問われる事態にもなっています。
世にはリーダーシップ論が溢れています。それだけニーズが高く、かつ答えが見つからないテーマだからなのでしょう。ですからリーダーシップ論は汎用性のある回答を提示しようとしますが、同時に個別的に考える必要があるのではないでしょうか。
なぜなら、リーダーシップは群を相手にしながら、突き詰めれば、それぞれに個性のある個々人に向き合うものだからです。
これだけリーダーシップ関連本が多く刊行されるのは、それだけニーズがあり、しかも訳の分からないものだからだと思います。
リーダーシップ論は、汎用性を旨としています。しかし、リーダーシップは個性のある個々人を相手とするため、個別性も同時に要求されはしないでしょうか。
ですから世のリーダーシップ論に学びつつ、自分なりにリーダーシップモデルを形成していくことが大事なのかもしれません。
 製品の製造に関して全責任を負っているのが工場長のAさんです。工場では100人以上が働いていて、彼らを統括するのがAさんなのです。
製品の製造に関して全責任を負っているのが工場長のAさんです。工場では100人以上が働いていて、彼らを統括するのがAさんなのです。
製造管理やライン・シフト調整といった仕事もAさんの大事な仕事でした。それ以外にもAさんには日課にしていることがあったそうです。工場内の見回りです。
午前と午後に各1回、工場内をぐるりと一回りします。ざっくばらんに部下と声を掛け合います。気になることがあればメモ帳を取り出して手早く書き付けることもAさんの習慣でした。
誰それの元気がない、このラインの製造がちょっと滞っている 等々。しかしある時期から、Aさんは工場歩きをしなくなります。
新たなプロジェクトのメンバーとして駆り出され、その時間がなくなってしまったというのがその理由です。
ただ、工場内の自室にこもって新たな仕事に取り組んでみると、集中できました。工場の流れも差し支えなさそうです。
しばらく経つと、自分が工場歩きをしていた習慣も忘れ始め、机に向かい切りとなりました。仕事の効率は格段に上がったとAさん自身には思えたのです。プロジェクトに関して、自分の考えをまとめ、文書に仕上げる仕事は大いに捗ったわけです。
一方で、工場の動きがどこかおかしくなり始めたのは、Aさんが満足げにレポートを見直しているのと同じ時期でした。
当初、こうした兆候にAさんはまったく気づかなかったといいます。
事情をおぼろげながらも把握したのは、事態がもっと深刻化してからでした。今では、月産目標に届かないラインがいくつもあり、欠勤も以前に比べて増えています。そして工場内の雰囲気が前よりも陰っているような気もします。
以前と今とでは何が変わったのか。
思い当たることは一つしかありません。Aさんの習慣だった工場歩きです。Aさんは社員との「接点」を失っていたのです。
 Aさんと部下の関わり合いは、工場歩きをやめてから、その形態が変化していました。 部下はAさんがこもる部屋のドアをノックするようになりました。以前はあまり見られなかった光景です。
Aさんと部下の関わり合いは、工場歩きをやめてから、その形態が変化していました。 部下はAさんがこもる部屋のドアをノックするようになりました。以前はあまり見られなかった光景です。
しかし、Aさんは別の仕事に没頭していますし、どこかで「つまらないことで自分を煩わせないで欲しい」という意識もあったのかもしれません。受け答えも雑になっていたような気がします。
もちろん、部下にはその都度、手短に指示を与えていました。短い時間で十分だと思いましたし、それこそがリーダーの能力の発揮どころだとも思えたのです。
効率的にリーダーシップを発揮しているつもりが、その結果はAさんが意図するのとはまったく逆です。Aさんはもう一度工場歩きをしてみようと考えました。
すると、待ちかねていたように部下が話しかけてきたのです。ほんのひと歩きしただけで、いろいろな情報がAさんのもとに集まってきます。
会話の一つひとつが工場の現状を把握する大事な要素でした。
話しかけられるたび解決策を話し合い、その場での解決が無理そうなら、この日のこの時間に話そうと、即座にスケジュールを割り振っていきました。
Aさんはリーダーとして、自分の問題を片付けようと工場を歩いてみたのに、それが誰かの問題を解決する機会となっていることに驚いたそうです。
プロジェクトの仕事にかかり切りになっているとき、部屋をノックしてくる者を自分の仕事への割り込み(邪魔)とみなしていましたが、実は、それこそリーダーシップを発揮する絶好の機会に他ならなかったのです。
リーダーの多くは、自分がリーダーの役目を引き受ける「理由」を理解しているものです。つまり、新たな挑戦であったり、影響力や威光の増大、あるいは報酬アップなどです。
つまり、リーダーはリーダーの地位から「何を得るか」を十分に理解しています。
ところが、リーダーの多くは、自分がリーダーの役目を引き受ける「目的」を十分に理解していないケースが多々あります。
つまり、リーダーはリーダーの地位から「何をもたらすか」を十分には理解していないのです。
リーダーは多忙な日々を送っています。次から次へと仕事が舞い込みます。部下との「接点」が自分の仕事への「割り込み」と感じられることもあるはずです。適当に済ませれば、そのときは時間を節約できるかもしれません。
しかし、部下は自分が尊重されているとは決して思いません。
長い目で見れば、部下にも、そして組織にも何ら「もたらす」ものはありません。
リーダーが「接点」において適切な行動を取れば、それは企業風土として根付き、強い組織が形成されていくのではないでしょうか。