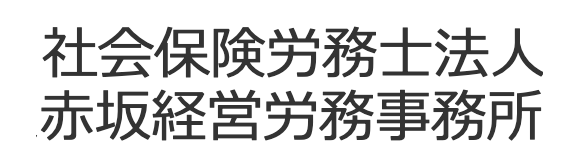A社は原料高の製品安という状況の中でも、順調に売上は確保してきたといいます。しかしながら、競争の激化とともに、いよいよ売上の減少が明らかになると、最初に声を上げたのは営業の中堅社員達だったそうです。
それは、「会社が苦しいのは分かっている。それだったら、かなりの時間を割いている社内研修を何とかしたらどうだろうか。正直なところ、研修に時間を取られるくらいだったら、それを営業に振り向けたい」というものです。
売上が落ちてまず突き上げを食うのは営業ですから、それを先回りした言葉だったのかも知れません。けれども、そこには研修制度自体に対する中堅社員の不満があったというのが根本だったようです。というのも彼らは、かねてより会社が実施する研修の必要性を疑問視していたからです。
A社の研修制度は、若手社員、中堅社員、幹部社員向けと対象を分けて行われています。
中堅社員に対しては外部の講師による自己啓発が研修の中心だったらしく、それは最前線で働く彼らにとって「理想論」でしかなく、会社の命令だから、出席せざるを得ないという程度のものに過ぎなかったようです。
定期的に開催していた中堅向けの研修が棚上げされたことで、営業に時間的な余裕が生まれたのは確かだったようです。しかし、時を経てみると、予想していなかった弊害が社内で見られるようになったといいます。それはまず、若手社員の研修軽視となって表れたそうです。「上がやってないのに何で自分達ばっかり」というのが彼らの言い分で、研修中の態度は明らかに「やらされている感」が強くなっていったそうです。
のみならず、研修がなくなったことで、営業に集中できるはずの中堅社員の成績も、半年経ってみても成果は芳しくありません。
 A社が閉塞感に包まれる中、A社長は発端となった中堅社員達を会議室に呼び出して、率直に「どんな研修だったら役に立つと思うのか」と訊いてみたというのです。
A社が閉塞感に包まれる中、A社長は発端となった中堅社員達を会議室に呼び出して、率直に「どんな研修だったら役に立つと思うのか」と訊いてみたというのです。
社員達がとつとつと話し出したのは、「もっと実践的であれば」というもので、その回答にA社長はしばらくの沈黙のあと、「それなら自分達でテーマを決めて、自分達の手で研修をやってみないか」と提案したそうです。それは、研修制度を再見直しするという社長の意思表示です。リーダー格のBさんを講師役に指名すると、1カ月後の開催を言い置いてその場を後にしたそうです。
最初は途方に暮れていたBさんでしたが、日頃から自分の課題として取り組んできたものにテーマを絞り、Bさんの選んだテーマは「いかに顧客単価を上げるか」というものだったそうです。それが身近なものであっただけに、研修は他の社員からも関心を得、好評を博する結果だったといいます。
この研修の成功がBさんにとって嬉しかったことは間違いありませんが、それ以上に、1カ月間夢中で研修準備の作業に没頭していたことに対する驚きと充実感のほうが、大きかったというのです。
Bさんが今回の件を通して強く感じたのは、「興味のない研修に受け身で参加するよりも、社員が積極的に研修に参加できる体制作りが大切なのではないか」ということだったようです。
Bさんによれば、最初は社長命令だったとはいえ、次第に知識の習得にのめり込みそしてさらには、その学んだ知識を他の社員に教えるという行為の楽しさに気づいたという体験が、Bさんにとって一番の成果であったというわけです。
以来、社員が講師となって行う研修スタイルは、持ち回りでA社に定着し、最近では「社内トレーナー制度」にまで発展しているそうです。
しかしながら、任命された社員にとって、講師になることは、新たな負担(通常業務との兼任)ですから、多少の手当をつけているそうです。
また、トレーナーとして教える内容は自分のキャリアプランに合致したものが選択でき、そのためにかかる経費は会社が負担するといった工夫がされているといいます。
経営環境がめまぐるしく変化する時代だからこそ、「強い組織」をつくるための教育体制の整備は重要な経営課題です。
投資にゆとりがなくなる状況においては、単にコスト削減により社内研修を減らしてしまうのではなく、研修の内製化、「社内トレーナーの育成」という視点で社内の教育体制を見直してみることも意味のあることだと思うのです。