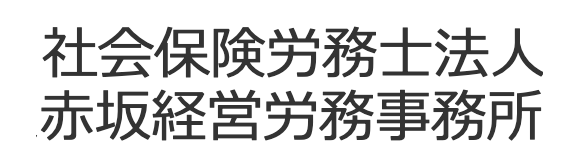店員が「訳の分からない顧客にからまれている」という知らせを受け、売り場の責任者が現場に急行しました。
店員が「訳の分からない顧客にからまれている」という知らせを受け、売り場の責任者が現場に急行しました。
事情を聞いてみると、こんな内容でした。客はズボンを買いました。しかし、その裾上げに2時間かかると聞いて自宅配送にしたのですが、その後、持って帰りたくなり、配送をやめて裾上げをしてほしいといってきたのです。
いったん宅配として預かったズボンを、“即日仕上げ”に戻すのは、縫製部門の状況次第では確かに面倒かも知れません。それに、宅配料として預かった料金の返還もあります。
そんな事情で“面倒”だと感じたのでしょう。
様々なものが複雑になり、しかも大量の業務をこなさなければならない昨今、傾向として現場が自分の効率を考えるあまり、 “顧客の立場”を感じ取れなくなったとしても不思議ではないでしょう。
しかし、ここに非常に大きな危険があるのです。それは、
“顧客の事情”を感じ取れないということは
“経営の事情”も感じ取れない
ということに他ならないからです。
以前より能力が劣っているのではないでしょう。自分の仕事をこなすのが精一杯という“複雑化”“大量化”の環境の中で、社内人材が“他者の立場”になってものを感じ取る“余裕”を失っているのだと思います。
そしてそれが、場合によっては顧客対応に表れ、また時として、以前では考えられないような「社内トラブル」を引き起こす原因になるのではないでしょうか。
熱心な業務指導が“いじめ”と捉えられたり、健康を気遣った言葉が“体型を指摘したセクハラ”に受けとめられたりするトラブルならまだしも、もっと根源的な“問題”が生じることもあるのです。
たとえば、
自分が正当に評価されないと不満を持つ従業員は、評価の難しさを実感できていない場合が多く、
給与に不満を持つ従業員は、会社が一定の利益を出すためにどれだけ多くのことをしなければならないかを実感していないケースが多いのです。
もし従業員が経営者に近い目線に立つようになれば、顧客の状況を理解して顧客に協力的になるばかりではなく、経営状況を理解してもっと経営にプラスの方向で仕事をするようになるかも知れません。
「他者事情」を感じ取る視点
 人事・労務
人事・労務