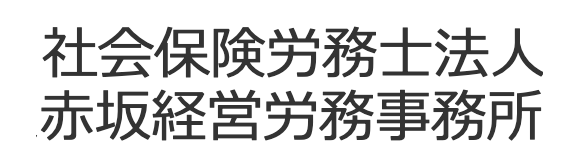同じ20人のチームが2つあったとします。それをAチームとBチームと呼びましょう。この両チームが、スポーツに挑戦することにしました。ただし、Aチームは100メートル走でBチームはサッカーです。
さて、両チームをコーチングするためのマネジメント手法は同じなのでしょうか。それとも違うのでしょうか。
Aチームのメンバー20人は、全員が100メートル走に取り組みます。全員が同じコトをするわけです。
もちろん、人の集まりですから、コーチングは簡単ではありません。個性に応じた練習指導が必要ですし、早熟型や晩成型などの違いを個々のメンバーから発見して、適切な能力把握を行わなければならないでしょう。
しかし、それでも、誰もが100メートル走での勝者を目指すという意味で、組織の管理は比較的容易なのではないでしょうか。多少の困難はあっても「アメとムチの政策」に、かなりの効果が期待できるはずです。
ただメンバー間で競争をさせるだけでも、チームはかなり健全に、力をつけて行くと考えられるのです。
ところが同じ20人のBチームはサッカーに取り組みました。そして、取り組む競技が変わっただけで、組織のコーチングは一変してしまうのです。
まず人材の適性を見抜いて、ポジションを決めなければなりませんし、そのポジションの役割を理解させなければなりません。自分のポジションの役割だけではなく、他者が何をするのかを深く知らなければならないでしょうし、何より、「チームとしてどんな戦い方をするのか」について、共通の理解が生まれなければ、決して勝てるチームは形成できないのです。
100メートル走がサッカーに変わるほど、私たちのビジネス環境は激変しているわけではありません。しかし、右肩上がりの経済成長環境が失われ、日本独特の、「業界全体で同じ方を向いて成長する(護送船団方式)」が崩壊した今日、確かに「誰にも分かりやすい価値観や目標を持つのは難しくなった」のではないでしょうか。
組織の中でも、出世や昇給をベースとした従来の“アメとムチ”の人材操縦術が通用しにくくなる一方で、社会全体の価値観も徐々に変化をし始めているからです。
短距離走とサッカーは違う
 人事・労務
人事・労務